「少数精鋭×プロフェッショナル」寺尾さんが語る、IT・インターネット業界に特化した人材エージェントの魅力
IT・インターネット業界に特化した人材エージェントとして、数々の実績とアワードを獲得している弊社。少数精鋭のプロフェッショナル集団の中で、コンサルタントとして活躍する寺尾さんに、なぜ弊社で働くのか、その理由を語っていただきました。 Q. 現在の仕事内容を教えてください。 寺尾:IT・インターネット業界の企業様に対して、人材紹介を中心とした採用支援を行っています。企業様の課題を深く理解し、最適な人材をご紹介することで、事業成長に貢献することが私のミッションです。また、求職者の方々に対しては、キャリアカウンセリングや求人紹介、面接対策など、転職活動全般をサポートしています。 Q. 弊社に入社を決めた理由は何ですか? 寺尾:大きく分けて3つの理由があります。1つ目は、少数精鋭のプロフェッショナル集団であることです。弊社は、一人ひとりの能力が高く、互いに刺激し合い、高め合うことができる環境です。これは、私の成長意欲を満たしてくれるだけではなく、顧客への良質な価値提供が出来るということに繋がります。2つ目は、IT・インターネット業界に特化していることです。私は、この業界のスピード感や変化の大きさに魅力を感じており、専門性を深めながら、業界の発展に貢献したいと考えています。また、業界の中でも良質なクライアント企業や、重要なポジションの採用を任せてもらっている事に、やり甲斐を感じています。3つ目は、代表の松井が納得度の高い判断とコミュニケーションをする事です。少数精鋭だからこそ、社長の判断や考え方がよく見えます。社長の考え方や人間性に疑問が出ると、どうしてもモチベーションに影響をします。何度もコミュニケーションを重ねて、そこに安心感を持つことが出来、入社を決めました。 Q. 実際に働いてみて、会社の魅力はどんなところだと感じていますか? 寺尾:やはり、優秀なメンバーと働けることですね。互いに尊敬し合い、切磋琢磨することで、常に高いレベルの仕事ができています。また、少数精鋭だからこそ、一人ひとりに大きな裁量が与えられ、自分のアイデアや意見を積極的に発信できる環境も魅力です。さらに、会社の成長スピードが速いことも魅力の一つです。常に新しいことに挑戦し、変化を恐れない姿勢は、私自身の成長を加速してくれますし、シンプルに飽きないです(笑) Q. 今後の目標を教えてください。 寺尾:まず
『Eight』が展開するリクルーティングサービス「成功の秘密:転職市場に革命を起こすサービスの裏側に迫る

今回インタビューさせていただいたのは、名刺アプリ『Eight』を提供するSansan株式会社に勤める平井利明さん(以下敬称略)。2019年にEightを活用したリクルーティングサービス「Eight Career Design」がリリースされましたが、Eightユーザー370万人を対象にスカウトができるうえ、そのユーザーの半数以上が管理職クラスという強みを活かして急成長を遂げています。今回は過去最高の成約を果たしたエージェントが、サービスの秘訣についてお話を伺う。 ▼平井 利明 Sansan株式会社 Eight事業部 求人広告や採用コンサルティングを展開する人材会社で事業責任者に従事。 『Eight Career Design』の可能性に魅力を感じて、2021年12月にSansan入社。 2022年よりエージェント向け新サービスの立ち上げに携わる。 ■『Eight Career Design』のリリース背景について〜出会いからイノベーションを生み出す〜 ── **寺尾**: はじめに、元々は名刺管理サービスだった『Eight』から派生し、リクルーティングサービスがなぜ始まったのかについてお伺いしたいのですが、『Eight Career Design』は2019年にリリースされ、すでに5年が経過していますね。元々の背景として、採用市場の競争が激化し、中途採用市場の有効求人倍率が1.6倍(2019年当時)という状況でした。現在では新規求人倍率が2倍を超えており、企業の採用意欲は依然高い状態です。このような状況を予測して、立ち上げられたと言えるでしょうか? **平井**: 立ち上げの背景についてお話しする前に、『Eight Career Design』のサービスについて簡単に説明させてください。このサービスには、「求人企業向け」と「エージェント向け」の2つがありますが、2019年の立ち上げ期は「求人企業向け(ダイレクトリクルーティングサービス)」としてスタートしました。それを踏まえたうえで背景をお話しします。 1つ目は、寺尾さんが仰ったように採用市場の競争激化と、採用市場のレッドオーシャン化の課題解決です。 転職希望者は就業労働人口の中でも一部であり、需給バランスが非常に歪な状況があり
【株式会社hacomono 代表の蓮田さんが語る、ウェルネス産業を新次元へ】

【プロフィール】 株式会社hacomono 代表取締役CEO 蓮田 健一株式会社エイトレッドの開発責任者としてX-point、AgileWorksを生みだす。2011年に震災で傾いた父の会社を継いだ後、再びプロダクトビジネスに挑戦するため、2013年7月に株式会社hacomono創業。 【最近の事業の状況】 ▼松井私自身、現在、2種類のジムに行っているのですが、両方の店舗でhacomonoが導入されています。既に6000店舗に導入されるなど、数字面からも成長が見て取れますが、最近の事業成長の手応えはいかがでしょうか? ▼蓮田当社の導入店舗数はフィットネスクラブに限らず、ダンススタジオ、インドアゴルフ、ゴルフ練習場、サッカースクール、カルチャースクール、サウナ、公共施設など幅広く増えています。 フィットネス業界だけをとっても市場全体が成長しており、これまでは市場規模が4000億円と言われていて、コロナ禍で落ち込んだ時期もあったのですが、2024年度には7000億円になるとまで言われています。 参考:船井総合研究所「フィットネス・ジム事業者向け フィットネス業界時流予測レポート2024 ~今後の見通し・業界動向・トレンド~」https://www.funaisoken.co.jp/dl-contents/jy-fitness_S055 DXによる生産性向上でもhacomonoが貢献できている実感はあり、分かりやすい例はchocoZAPやピラティス、24時間ジムなど業態の多様化・多店舗化があります。当社も引き続きDXを通じて、市場規模 1兆円超えに貢献していきたいです。 ▼松井コロナ禍から脱して、フィットネス市場が拡大をしているのですね。hacomonoを導入しているフィットネスクラブの経営者の方々の記事を拝見したのですが、20代中盤の方が、創業2年で40店舗以上展開するなど、フィットネス業界が多様化しながらも、急成長していることを知って驚きました。 ▼蓮田当社のシステム「hacomono」を使って、数年で数10店舗展開しているジムはどんどん増えています。また、大手企業も新ブランドを立ち上げる際に当社を活用するなど、業界全体の成長と多様化に貢献できている手応えがあります。 ▼松井蓮田さんは、日本のフィットネス参加率を3%から10%に引き上げる取り組み「PROJECT 3
株式会社HERP 代表の庄田さんが語る『採用を変え、日本を強く。』

▼プロフィール株式会社HERP 代表取締役庄田 一郎京都大学法学部卒業後、リクルートに入社。 SUUMOの営業を経て、リクルートホールディングスへ出向後、エンジニア新卒採用に従事。その後、株式会社エウレカに採用広報担当として入社後、同責任者に就任。カップル向けコミュニケーションアプリ『Couples』のプロダクトオーナーを経て、2017年3月に株式会社HERPを創業。 【庄田さん幼少期】 ▼松井庄田さんとは、リクルート社からエウレカ社へ転職される際に支援したのがきっかけで、すでに10年近いお付き合いになるのですが、庄田さんの転職相談に乗った初対面時に、メチャクチャ心を開いてくれなかったことを覚えています(笑)。また、学歴・実績・コミュニケーション能力といったスペックの高さがあるにも関わらず、ご自身のことを「コンプレックスの塊」だと言っていたことが印象的でした。庄田さんは、一定のトガリがあった時期から転職や起業を経て、かなり人柄がマイルドになった印象があります。 ▼庄田最初は、メチャクチャ様子を見ていました。というよりも、昔から人を見てしまうタイプなんですよ。人を見る癖がついたのは、自分の強いコンプレックスが原因です。基本的に「自分はまだまだダメだ」と思い続けてきた人生で、「もっとやれる」「もっと良くならないとだめだ」という根拠も正確な目標もない漠然とした“不安”を持ち続けてるところがあります。そのコンプレックスが芽生えたのは幼少期の経験がベースだと思っていて、元を辿ってみると両親のコミュニケーションが「あなたは努力をしていないのでもっと頑張りなさい」というような基本姿勢だったことにあると思います。だからこそ、周りの人たちをよく観察して、「どうやったらあんな風にできるんだろう?」と、よく考えるタイプになりましたね。勉強やスポーツに関してはもちろんですが、コミュニケーションにおいてもコンプレックスが強くて、先天的にコミュニケーションが得意な人たちと接する度に「すごいなぁ」とか「どうやったらあれができるようになるのかな」とか考え続けていました。逆に、誰かと二人きりになるのが苦手で、「ここで何を話すことが正解なのか?」と考えてしまうが故に何も言えなくなるというようなことも昔は少なくありませんでした。 ▼松井そのような原体験から、人を観察するようになったのですね。ただ、庄田
【MNTSQ株式会社で働くことの意味合い】

【エンジニアがMNTSQ社で働く魅力】 ▼松井現在、開発部門をマネジメントしている高田さんが、私経由でMNTSQ社に入社をして1年超くらいでしょうか。今の高田さんにとってMNTSQは、どんな会社なのでしょうか。 ▼高田私は『すべての合意をフェアにする』というビジョンに強く惹かれています。このビジョンは、曖昧ですが、達成された時には、世界がきっと良くなるという感覚があります。その世界を見てみたいと思いますし、自分たちで実現させたい。板谷は、それをリードしてくれる存在であり、私は、支えていきたいと思っています。 ▼松井『すべての合意をフェアにする』ことで世界が良くなるという感覚は、入社時からの感覚なのでしょうか。 ▼高田入社時には、分からなかったです。入社当時、「合意」とか「契約」は、これまでの社会人経験の範囲で、ぼんやりとイメージをしていました。そこから私の場合、カスタマーサクセスから入って、顧客と向き合う機会が多く、解像度が明らかに変わりました。また、プロダクトの成長やマーケット環境の変化によって、その影響力を実感出来るようになってきたように思います。戦略や戦術がいかに変化しても驚かないですが、根本である『すべての合意をフェアにする』といったビジョンが変わったら、少し動揺するかもしれません。そのぐらい、会社としても、個人としても、このビジョンが柱になっていると思います。 ▼松井なるほどです。高田さんはMNTSQ社で働いていく内に、『すべての合意をフェアにする』といったビジョンに、どんどん魅力を感じていったのですね。その高田さんから見て、エンジニアの方々がMNTSQ社で働く魅力って、何だと思いますか。 ▼高田人それぞれだと思うので、言語化するのは難しいところがありますね。MNTSQ社に間違いなくあるのは、「AI技術を活用していること」「課題解決をプロダクトで行っていること」「リーガルであり、エンタープライズ向けであること」そのような特徴があるものの、何が魅力になるかは個々人に依ってきます。あとは、結局、魅力に感じてもらうのは、組織自体であることが多いです。 ▼松井組織の魅力を、どのように伝えているのでしょうか? ▼高田今回、当社が新組織になった経緯も、会社として課題感を感じていたからです。その課題感を正直にお伝えすることで、当社で活躍できるイメージを具体的に共有する
MNTSQ株式会社 代表の板谷さんが語る『弁護士からIT経営者へ』
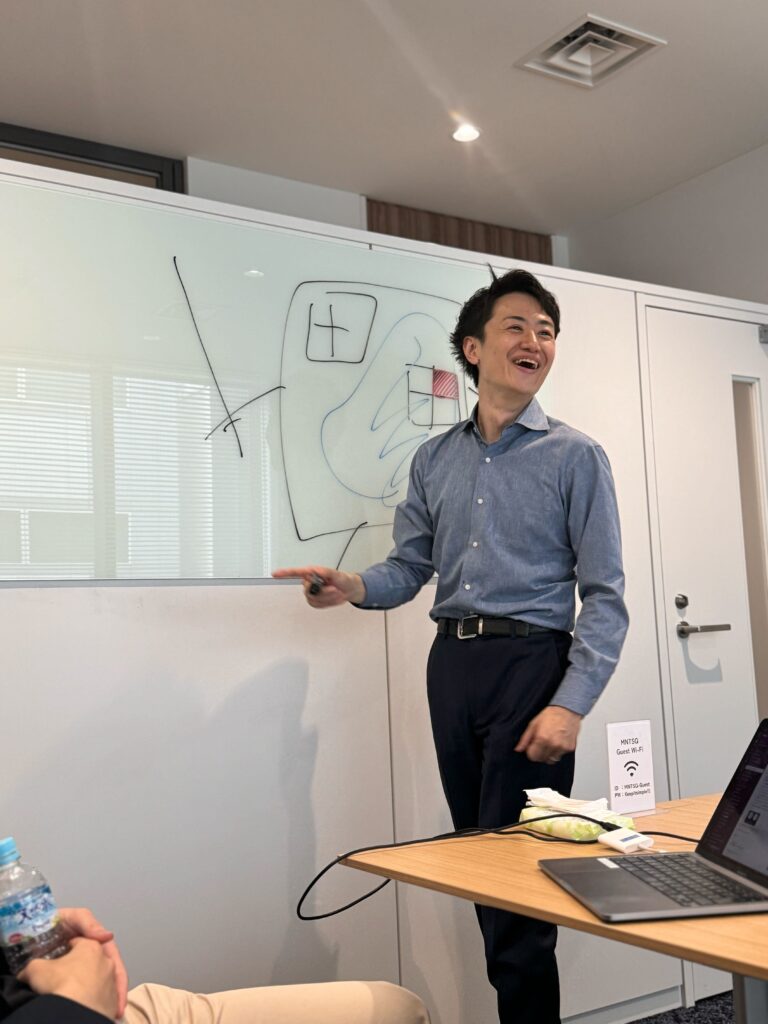
【MNTSQ社 創業経緯】 ▼松井MNTSQ社は創業時からお付き合いをさせていただき、何名もご入社いただいてきましたが、改めて、板谷さんが創業した経緯を教えて頂ければ ▼板谷私は長島・大野・常松法律事務所(以下、NO&T)で弁護士として働いていたのですが、仕事自体は非常に楽しかったです。 ある時、大手金融機関をクライアントとして、スタートアップ企業に融資する案件を担当しました。私は金融機関側の弁護士なので、端的に言えば、金融機関がリスクを最小化出来る契約書を作成しました。その後、相手のスタートアップ企業の代表から電話があったことから、契約内容を、もう少しスタートアップ企業寄りに変更をするための相談だと予想していたのですが、実際には、「板谷先生に対して全幅の信頼をしているので、進めてください。これで当社の事業を加速化できます。今回は本当にありがとうございました!」という感謝の言葉とともに、契約の締結をいただきました。 顧客である金融機関の利益を最大化出来た訳ですし、その取引先の代表も喜んでいる。弁護士としては良い仕事が出来たのかもしれません。ただ、「社会のため」の事業を行っている起業家に対して、私は「顧客のため」の仕事は出来たものの、「社会のため」の仕事が出来ているのか。そう考えた時に「顧客正義よりも社会正義を優先したい」「社会のために働いていきたい」といった思いが明確化されました。 また、目の前の顧客のために働いたとしても、世の中では年間に5億件の契約が締結されています。1件1件のベスト・プラクティスを目指す仕事も重要ですが、私がやりたいのは、ベスト・プラクティスを世の中に広げていき、皆さんに活用してもらうこと。ある意味で、エンジニアがオープンソースに貢献していくように、社会に役立つ法律のプラットフォームを作っていきたいと考えるようになりました。 【プロダクト化】 ▼松井 その後、大学の同級生でもあり、AIトップ企業のPKSHA Technology社の経営チームにもいた安野さんや堅山さんと相談して、プロダクトを作られたと記憶していますが、プロダクトを作るまでの過程はスムーズだったのでしょうか。 ▼板谷 まずは、「世の中に広く使ってもらえるプロダクトを作る構想は面白いよね」という話で盛り上がりました。 また、幸運だったことに、PKSHA Technolog
【中途面接と新卒面接の違い】

▼中途面接を苦手とする方々 キャリアを積み重ねている方でも、転職活動の経験が浅く、面接を苦手としている人も少なくないです。理由の一つが「新卒時代の面接イメージを引きずっている」だと思います。「企業側に気に入ってもらおう」「合格をしたい」という気持ちが強くて、相手に合わせてしまいます。相手に合わせて話す人は、魅力が低減してしまいますし、思うような結果を得ることが難しいです。生き生きと、自身を表現する意味でも、中途面接は、新卒面接とは違うスタンスで臨んだ方が良いと思います。 ▼中途面接でのスタンス それでは、中途面接では、どのようなスタンスで臨むのかを整理していきたいと思います。 1.「やりたいこと」より、「できること」を中心に伝える新卒採用は基本的に、ポテンシャル重視です。そのため、面接では将来の「やりたいこと」を中心に話すのがセオリーです。 一方、即戦力になるかどうかを見られる中途採用の面接では、それ以上に今「できること」を伝えたほうが良いです。転職希望者の中にも、「新規事業を立ち上げたい」「経営に近い仕事をしたい」というように、「やりたいこと」を中心に語る方々もいます。しかし、たとえば「どんな新規事業ですか?」と質問すると、残念ながら具体的なアイデアが出てこないケースがほとんどです。また、経営に携わりたいと言う方も、会社経営に伴う泥臭い実務や、社員の生活を背負うリスクなどの現実に目を向けられていないことがよくあります。 企業側としては、こうした方を積極的に採用することはありません。「経験がない、やりたい仕事」にチャレンジしても成果が出ない可能性が高いですし、その人にマッチした「できる仕事」にアサインしても「やりたい仕事ではない」と不満を持つリスクが大きいからです。新卒採用の時と違って、採用する側は「可能性」ではなく、「現実」や「成果」を期待します。冷静に自己分析を行い、面接では自分が実際に「できること」を語りましょう。 2.「抽象的な夢」より、「明日の結果」の話をする「3年後には、こんな事業を作りたい」「5年後には、独立したい」などというように、中長期的な目標を持つことは素晴らしいです。また、自分や世の中がどのような変化をしていくかを、想定していることは、非常に大事なことだと思います。ただ、その内容に具体性がなかったり、「お金を稼ぎたい」「偉いと思われたい」とい
【30代後半以降の転職が難しくなる理由】

以前は、「35歳、転職限界説」のようなものがありましたが、現在は35歳を過ぎた転職も珍しくないです。実際、弊社の転職サポートの実績は、毎年7割〜8割が35歳以上です。 ただ、30代よりも40代。40代よりも50代のほうが転職が難しくなる場合が多いです。年齢を重ねるほど、転職を難しくしている理由や、それをクリアにする方法を整理したいと思います。 ▼NGになる理由 年齢を重ねるほど、NG理由として・実績の分、プライドが高くなり、自分が正しいと考える(=周りが間違っていると考える)・体力が落ちて、アンラーニングが難しくなる・家族のケアで、仕事に集中しきれない場合もあるという内容が多くなります。 実際、候補者の方と話をしていて、勿体無いなと思うのは、「もうトシなんで」という言葉です。今日が人生で一番若いのに、これからずっと「もうトシなんで」と言い続けるのかなと思ってしまいます。また、「精力的に働こう」「柔軟に自分を変えていこう」という人材に見えないため、採用したい企業は少ないと思います。 ▼評価される理由 一方で、経験豊富な方々を採用する理由は、・数多くの「成功体験」「経験」「人脈」を持っていて、それらを活用して結果を出してくれる・選択肢が限られている。その分、事業や組織にコミットしてくれる・自分の事よりも、結果を優先して動くことのメリットを知っているといった内容が多いです。 実績や人脈は、料理に喩えると、食材です。持っているだけでは価値が薄いですが、きちんと活用すると、素晴らしい結果を生み出すことが出来ます。 また、キャリアとして、選択肢が少なくなる分、「向こうの会社のほうが面白そう」と変に迷うこと無く、「まずはこの会社にコミットして結果を出す」と肚が据わっている場合も多いです。特に経営者は、会社の風土を醸成する意味でも、メンバーのコミットメントを重視しています。腹を据えている社員の方がいると、周りにも良い影響があり、有益な存在だと感謝をされると思います。 ▼総論 整理をすると、「過去」や「自分」に拘泥する人は敬遠されます。また、体力がない人も同様です。 話をしている中で、「もう、この年齢なんで」「企業側の話を聞いても良いですよ」などの言葉が出たら危険信号だと思います。 もちろん、プライドを持つことを否定しないですし、その言葉が似合うだけの実績を出している方もいます。た
【なぜ、転職活動で本気を出さない人は多いのか】

転職に時間を割けない理由は、「仕事を抱えているから」「家族がいるから」「努力するものではないから(=選考は自然体で受けるべきものだから)」「努力しても結果に繋がるとは限らないから」といった理由をお話される方が多いです。 上記に加えて、「本気で向き合って、企業側からNGが出たらショックなので、言い訳の余地を残している」「努力の仕方が分からない」といった理由もありそうです。 ただ、「人生の分岐点であること」「その割には、競争が激しくないこと」を考えると、「本気で取り組んだほうが良い」と考えます。 【転職が、効率的な投資である理由】 転職は、僅かな努力と時間投資で、大幅なレベルアップが可能です。 たとえば、高学歴を獲得するには、数年間の勉強が必要なことが多いです。また、新卒時の就職活動においても、インターンや面接、エントリーシートなどを含めると、1年以上の努力が必要です。このように、学歴や新卒就職で、納得度の高い成果を出すためには、1年〜数年の努力が必要です。これは、なぜかと言えば「周りも一斉に努力をするから」「競争が激しいから」です。 一方で、転職活動に、それだけの労力を投資する人は、ほとんどいないと思います。履歴書、経歴書を作成をして、何社かの面接を受けて等、だいたい、数ヶ月くらいの時間を投じて、自然体で話をして、相性が合ったところに行くというのが通常だと思います。 本業を抱えている上に、プライベートが忙しくて、時間が捻出できないのも理解が出来ます。一方で、学歴、新卒時と比べると、圧倒的に競争が少ないというのも事実だと思います。競争が少ない上に、仕事や年収と、直接的な関係がある転職活動に、人よりも時間や労力をかけるのは、効果的な投資だと言えます。 【具体的に、どのような努力をするべきか】 では、実際に、どのような努力をするべきでしょうか?全てに言えることですが、「長時間かけること」ではなく、「どれだけ本質的に行うか」が大事だと思います。 ①自身の整理 まずは、オーソドックスですが、履歴書、経歴書の作成や、マインドマップやプレゼン資料を作成して、自身のキャリアの棚卸しを行います。転職先を検討する際には、・事業内容(成長性&意義)・仕事内容(成果&成長)・人的環境(好き&尊敬)・待遇(年収&ポジション&キャリア)などで決めていく形が良いかと思うので、その点を意識した、キ
【経歴書の書き方の注意点】

【そもそも経歴書とは?】 経歴書は、「どのような環境の中で、どれだけの実績を出してきたか」「その実績を、環境を変えて、どのように活かしていけるか」を理解するための説明書とも言えます。多くの人が「詳細に、過去の経歴を伝えようとする」「志望理由などで熱意を伝えようとする」のですが、それは「nice to hava」くらいで「must have」ではないです。 経歴書には、・あくまで過去のもので、未来を作れる訳ではない・自己申告制なので、盛った内容も書けるといった欠点があります。 「過去」「主観」の時点で、「未来」「客観」を重視する選考過程においては、一定の充実度で良いと考えています。 【経歴書以外でアピールする方法】 それでは、経歴書以外でアピールするには、どのような方法があるでしょうか? ①企画書にコダワル おそらく企業側が喜ぶことの一つは、企画書を作成してくることです。どのようなフォーマットでも良いので、入社後のアウトプットイメージを詳細に作ることで、企業側と詳細に擦り合わせが出来ると思います。これによって、企業側が安心に採用に踏み込める他、候補者側も、「こんなはずでは、なかった」という期待値のギャップが生まれづらいと思います。 ②実際に、使ってみる。やってみる。作ってみる ・選考を考えている企業の製品やサービスを、ユーザーとして使ってみる。・競合企業のものも使ってみる。・顧客として、接してみて、相手の反応を確認してみる・入社した時に想定される動きを、入社前にやってみる。・似たようなサービスを、自分なりに作ってみる。 ③実際に働いてみる 副業のような形で、一月〜数ヶ月、実際に働いてみる。これが一番正確に相性が見えると思います。メリットは、「ミスマッチが生まれづらい」「入社した場合の立ち上がりが速い」デメリットは、「立ち上がりが速くない、大器晩成型のタイプの候補者を落としてしまう」「幻滅期に判断するタイミングがある」などが考えられます。 【経歴書でアピールした成功例・失敗例】 経歴書は学歴に近いです。過去の優秀さの一つの指標になりますし、その人のことを一定表していますが、詳細を保証するものではないです。とはいえ、ほとんどの選考が経歴書から始まっているように、ここで優劣が付くことが多いのも事実です。 経歴書で上手くいった事例と失敗した事例について、記してみます。 ▼成
